「脱水」と聞くと暑い夏に起こるイメージですが、冬にも起こりやすいというのはご存知でしょうか?
とくに、この時期は、知らず知らずのうちにからだから水分が奪われ、水分不足気味になってしまう「かくれ脱水」に注意が必要です。
今回は、そのような「冬のかくれ脱水」を防ぐためのポイントを薬剤師がお伝えします。
(文/薬剤師 竹田由子)
冬に起こりやすい「かくれ脱水」とは?
「かくれ脱水」とは脱水症の一歩手前で、自覚症状がないまま体重の1%相当の水分が失われた状態をいいます。
乾燥している冬は、気づかないうちに皮膚や呼気から水分が蒸発し、1日に約1リットルもの水分が体内から失われています。
また、冬は喉の渇きを感じにくく、水分を摂る機会も減ってしまうので、脱水症状が進行しやすくなります。
1.この症状に当てはまる方は「かくれ脱水」かも!?
次の項目は冬にあらわれやすい「かくれ脱水」のサインです。
・便秘がちになる
・冷えやむくみが気になる
・肌にツヤがなくなる。皮膚表面がポロポロ落ちる
・唾液の量が減り、飲み込めなくなる
いくつか当てはまるようでしたら、かくれ脱水を疑ったほうがいいかもしれません。
2.「かくれ脱水」はダイエットにも影響する
かくれ脱水はダイエットにも影響を及ぼすことがあります。
からだに水分が足りていないと、栄養や酸素を十分に運ぶことができなくなるので、エネルギー不足となり代謝が悪くなります。
代謝が悪いと脂肪を燃やすことができなくなってしまうため、ダイエットが成功しづらくなるのです。
また、かくれ脱水の状態でからだに負荷のかかるダイエットを行うと、脱水症に進行しやすくなるため注意が必要です。
「かくれ脱水」を予防する正しい水分補給方法
体調を良好に保つために、冬でも意識して水分を摂ることが大切です。ここでは、正しい水分補給の方法をお伝えします。
1.水や麦茶がおすすめ
水分補給には、水やミネラル豊富な麦茶がおすすめです。コーヒーや緑茶には利尿作用があるため、脱水対策として摂るのは避けたほうがよいでしょう。
2.温度は冷たすぎず、熱すぎず
水の温度は、常温もしくは11~15℃くらいが理想的です。冬場はからだを冷やさないように、ぬるめの白湯にしてもいいでしょう。
3.こまめに継続的に補給する
からだが水分を一度に取り込める量は限られているので、少しずつ継続的に補給することが大切です。
目安としてはコップ1杯程度を、起床後・食事時・休憩時間・入浴前・就寝前など、ご自身の生活のタイミングに合わせて摂るようにすると、無理なく継続できます。
更年期は意識的な水分補給を!
女性の閉経前後に当たる更年期には、とくに意識して水分を摂る必要があります。
更年期にはホルモンバランスが乱れることで、ホットフラッシュ(のぼせやほてり)や水分代謝の過度な進行などが起こり、何もしなくても水分が不足してしまう傾向にあるからです。
更年期症状にかくれ脱水が重なると、体内の水分不足で血液が濃縮され、脳梗塞や心筋梗塞を引き起こすリスクが高まります。
また、尿量が減って細菌を洗い流しにくくなるため、膀胱炎を起こしてしまうこともあります。
「かくれ脱水」には漢方も取り入れて
お伝えしたような方法で水分の摂り方を意識すれば、冬のかくれ脱水は予防できます。
しかし、冬は汗をかきづらいため水分を摂り忘れてしまったり、トイレの回数が気になったりと、なかなか実践しづらい方もいるかもしれません。
そのような方には、からだの内側から体質改善ができる漢方薬がおすすめです。漢方薬は、体内の水分の乱れ、血(けつ)の不足や流れの滞り、気の流れの異常などを整えることで症状を根本から改善します。
漢方は飲むだけで手軽に始めることができますし、からだに優しい成分で作られているため、副作用も起こりにくいといわれています。
まずは、かくれ脱水が原因で起こる冬の諸症状におすすめの漢方薬をご紹介します。
<冬のかくれ脱水にお悩みの方におすすめの漢方薬>
・麦門冬湯(ばくもんどうとう):乾いた咳、喉の乾燥が気になる方に
不足した水分を補い、肺をうるおします。
・当帰飲子(とうきいんし):皮膚の乾燥、かゆみが気になる方に
カサカサ肌に栄養分とうるおいを与え、乾燥肌を改善します。
・潤腸湯(じゅんちょうとう):便が硬く、便秘気味の方に
腸をうるおし、排便を促します。
また、更年期が冬のかくれ脱水を進行させていると考えられる方は、更年期症状によく使われる漢方薬を使ってみるのもよいでしょう。
<更年期症状にお悩みの方におすすめの漢方薬>
・加味逍遙散(かみしょうようさん):イライラや肩こり、めまいなどの更年期症状に
自律神経を調整し、イライラやのぼせを鎮め、血行も促進します。
・柴胡桂枝乾姜湯(さいこけいしかんきょうとう):冷え性で、動悸や息切れなどの更年期症状に
こもった熱を発散させ、体力を補います。口の乾きや頭部の発汗にも用いられます。
・温経湯(うんけいとう):冷え症で、手足がほてり、唇が乾燥しているような人に
血の量が不足した血虚(けっきょ)を改善して温めていく漢方薬です。
漢方は体質改善を目的としているため、このように今ある症状を抑えることはもちろん、不調の原因からアプローチすることも可能です。
しかし、どの漢方薬が今の症状に合い、ご自身の体質に合っているのかを見極めるのは難しく感じるかもしれません。
症状や体質にうまく合っていないと、効果を感じられないだけでなく、場合によっては副作用が生じることもあるのです。
漢方薬を選ぶ際に不安を感じる方は、「あんしん漢方」などのオンライン漢方サービスがおすすめです。漢方に詳しい薬剤師が一人ひとりに効く漢方薬を見極めて適切な漢方薬を見つけてくれ、さらにお手頃価格で自宅まで郵送してくれます。
▶「あんしん漢方」を詳しく見てみる
「冬のかくれ脱水」は知っていれば予防できる!
「冬に脱水」という認識がないと、冬のかくれ脱水は気づかないうちに進行してしまうこともあります。
また、夏に比べて運動量が低下したり、入浴が長時間になったりすることも、冬のかくれ脱水の原因となります。
これらは水分を意識して摂ることで防げるので、ぜひお伝えした方法を試してみてください。
<この記事を書いた人>
薬剤師 竹田由子
大学院で臨床薬学を専攻、病院で10年勤務、結婚後は調剤薬局勤務、ライターとしての活動も始める。腎機能低下を機に、月経痛への鎮痛剤使用量を漢方で減量成功した経験がある。元漢方・生薬認定薬剤師で薬膳漢方マイスター。「日常の不調はまず漢方」をモットーに生活を送る。病院時代の長いDI経験を生かし、薬の面から分かり易くサポートしたいと考えている。
▶あんしん漢方(オンラインAI漢方)












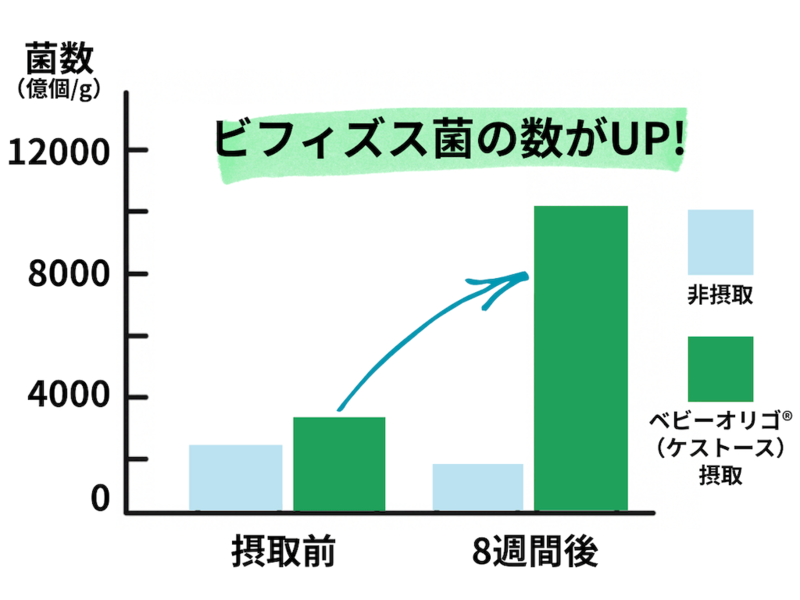

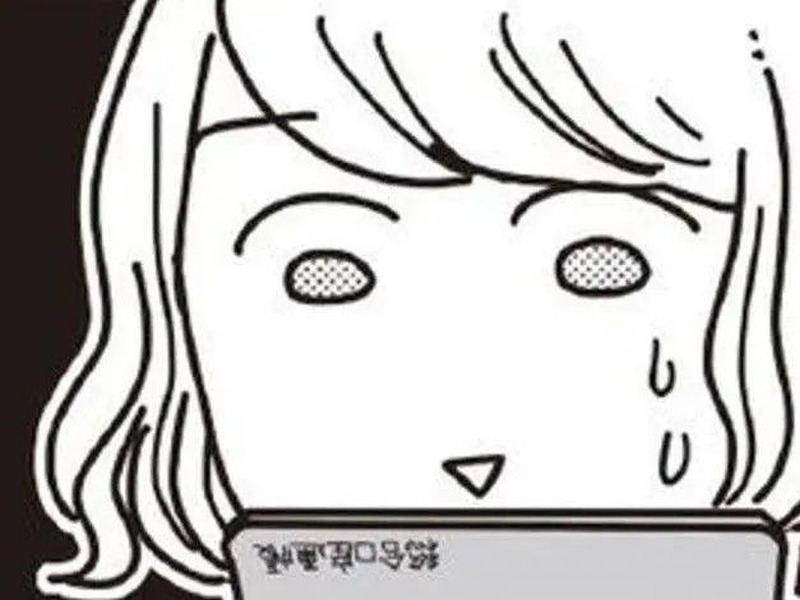



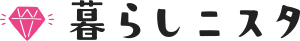


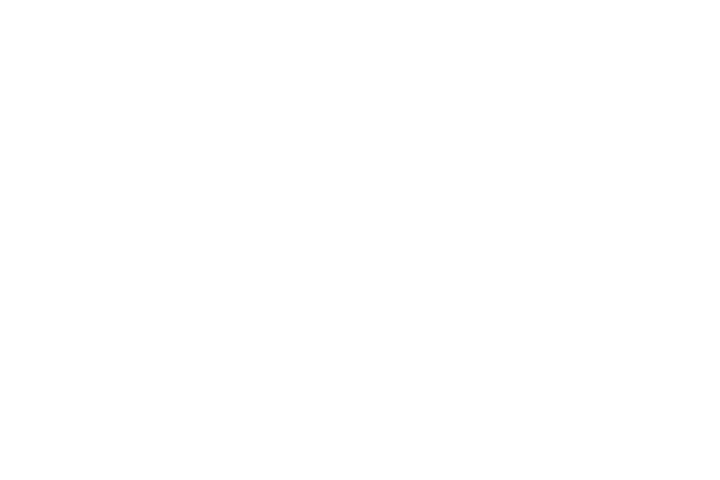
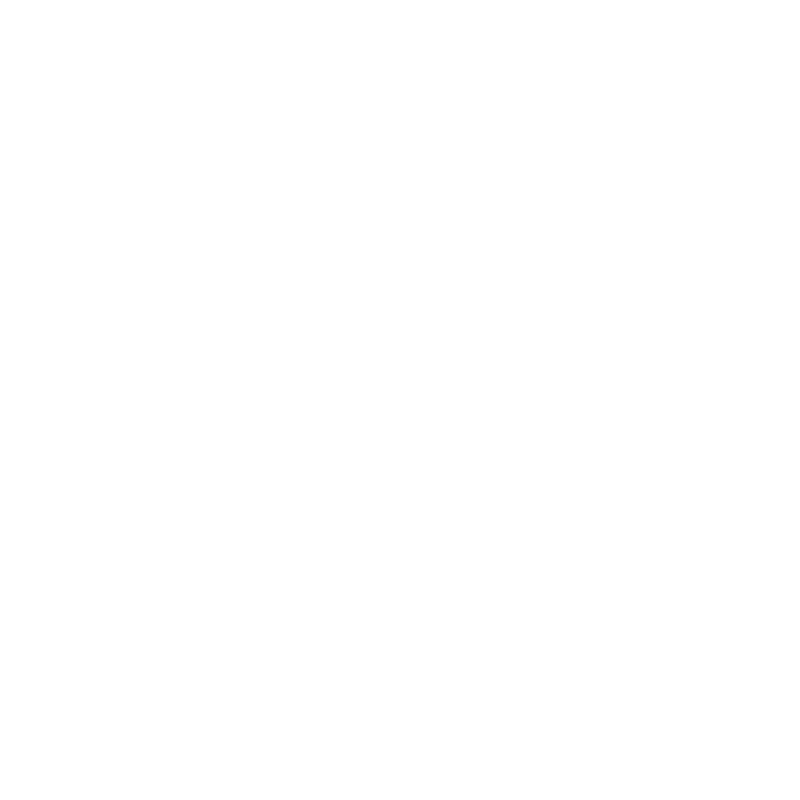
![[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひどい肌トラブルを救ってくれたのはコレでした」](http://img.kurashinista.jp/get/2025/11/26/93c18d7d3165c4c47e065f488a61a5ef.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...
[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...![[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベビーから大人まで使えるこのスキンケアの実力とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/652a60fa2cd3a587a9a42d7164dad1c1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...
[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...![[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キッズ ベビーオリゴ®」が選ばれる理由とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2025/12/31/240a8d7521e72fb6ab5027cf72b2e102.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...
[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...![[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり・やわらか・伸び~る肌に!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/1649bec205350eddf0f29d2df2476ac8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...
[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...![[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う? 赤のジェリーでおなじみ「アスタリフト」たった7日試しただけで「わかったこと」とは!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/09/9baa7cd6aa648b5f68a397f6e1c292d8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...
[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...![[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝も、腹ペコな午後も。私たちが『超熟』を選ぶ理由って?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/26/d0a6213d838b9a06de95e683d0c14391.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...
[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...![[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家庭で効率よく向き合うケアアイテムが新登場!骨盤底筋専用EMS「SIXPAD ペリネフィット」](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/87aab1fc469c237111f888f1820fa561.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...
[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...![[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料理、ものづくり体験など魅力満載。【只見線】の旅の楽しみ方](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/6e401437f5ed3d32fe88e08a32f838e1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...
[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

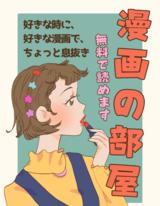












































コメント
全て既読にする
コメントがあるとここに表示されます