
◀初めから読む 母子の部屋は、一階にあるその角部屋である|うさぎの耳〈第一話〉
あまり期待してはいけない、と自分に言い聞かせていた。
彼女は、昼下がりのいつもの公園で、たった一度出会っただけの女性だ。思えば名前も訊いていないのだ。
ベビーカーの中の理玖の顔を見て、リクくん、とかすれた声で呼びかけてくれた。長い髪は少し色落ちしたように先が細く、それでも艶めいて風になびいていた。
その声や髪はよく覚えているのに、どんな顔立ちだったか、目や口元の形に至るまで記憶が曖昧だった。
緑色のパペットを理玖にくれて、編み方まで教えてくれると言っていた。しかし、これから冬になっていく公園で?それに彼女は本当に月曜日と金曜日には公園にやってきて、寒空の下、編み物をしているのだろうか。なぜわざわざ公園で時間を過ごしているのだろう。私たちのように、家にいられないわけではないだろうに。
窓辺に置いた緑色のパペットは、今、カーテン越しに朝日を浴びて、ちょっとおどけているように見えた。ピンクの鼻の上で、二つの目玉が寄り目になって見える。
「お義母さん、買い物は、メモにある通りでいいですよね?あとすみませんが、今日は少し余分にほしいんです」
義母がキッチンでコーヒーサーバーからカップにコーヒーを注いでいるのが、音でわかる。理玖を抱いてリビングに出ていき、そう頼む。私の腕の中をちらっと見やったきり、まるでこの世に理玖は存在しないように目を逸らす。私のことも、よくは見ようとしないから、視線の置き場に困って見える。
「そうね、メモ、渡したわよね」
食材などの買い物は、理玖のおむつや、緊急用の粉ミルクもあるから私の役だ。帰りにベビーカーの後ろにぶら下げて帰ってくる。そういうものが、箱で宅急便が届くのも、義母は嫌がる。
頼まれる買い物はとても具体的で
〈薄くスライスしてあるかぼちゃ
豆乳(いつもの薄い方)
クレソン、二束
茗荷 三つくらい
エゴマの葉
茹で蛸、足一本くらい
塩サバ(一夜干し)
牛肉 小ぶり ロース 和牛〉
などと、縦書きの達筆が続く。メモを書くにも、万年筆の文字。そんなことだけでも、義母には大切にしている生活があるのがわかる。それはそれで、ご立派だ。
けれど、理玖と私にも暮らしがある。遠慮してばかりなんていられないのだ。もちろん食材は自分の分も買わせてもらうし、理玖は離乳食も始まった。お尻拭きや瓶詰のベビーフードも買う。自分が食べたい時にはビスケットや、よくあるいちご味のチョコレートやレジ横に並んでいるみたらし団子なども買う。
「余分っていくらくらい?けちで言ってるんじゃないのよ。わからないじゃないの。何に使うの?」
義母は午前中はネグリジェの上にガウンを着ている。もう六十代後半なのに夜更かしで、深夜まで映画チャンネルで映画を観ているようだ。低血圧で、朝は苦手。その年齢なのに、というのは可笑しいのかもしれないが、義母は少なくとも枯れてはいない。以前は六十代後半の人など、人生において達観の域に向かっているのかと想像していたけれど。
夕方になると綺麗なウールのセーターに明るい色のパンツなどにはき替えて、髪の毛を整えて、うっすらメークもする。そして、俳句のノートを手に、少し近所を散歩する。帰ると自分の食べたい料理を私に頼むか、気が向けば自分でも作る。いつも白ワインを二杯くらい飲むようだ。
食事は別々だから、洗い物の食器からしかわからないが、昼食も夕食もきちんと旺盛に摂っているのがわかる。
「毛糸や手芸用具を少し買いたいんです。それと、保温ポットを」
「じゃあ、一万円もあればいいわよね」
重たい瞼をこちらに向ける。
「助かります」
私は義母の大きな財布から直接抜き出されたお金を、生活費用を収めるために渡されている、えんじ色の大きながま口財布に移した。
「あのね、美夏さん、手芸とかって、あなた、できるの?この家に変なもの増やさないでね」
出がけに、背中に向かって釘を刺された。
理玖が手に握りしめていた緑色のパペットが目についたはずだ。そういう嫌味をわざわざ言うのも、思わず寄せてしまう関心の裏返しに聞こえてくる。
「さあ、どうなることか」
「ちょっとあなた、何よその口ぶりは。やめてね、って言っているんだから、答えは、はいでしょう?」
「行ってきます」
一々、玄関脇の物置に畳み入れる約束のベビーカーを取り出して足で開き、理玖をシートに乗せる。首がすわってきたから、体は起こし気味にでき、二人で出かけているのだという気持ちが以前より大きくなった。ベージュの羽毛のブランケットをかけて外に出た。それは、義母の俳句仲間がお祝いに買ってくれたものらしくて、ずっと重宝している。
外気が冷たく、心地よい。
「理玖、今日はちょっとお出かけするよ」
どこからか風に乗って枯葉が舞い降りてきて、ブランケットの上に、一枚の絵のように載った。
彼女との再会は、あっけないほど早く訪れた。翌月曜日、以前と同じベンチに座っていたら、また髪の毛をふわりと揺らした女性が公園に現れたのが視界に入ったのだ。
自分のベンチから遊具を挟んで対角線側、公園入り口近くのベンチに、その人がすっと腰かけたのを見つけて、立ち上がった。
「こんにちは」
聞こえる距離ではないのに、声をあげていた。だが彼女は、気づいてはいないようだった。またはそっとしておいてほしいのかもしれない。
どうしようか、近づいて話しかけてよいものか戸惑って、もう一度勇気を持って頭の上高くで手を振ってみた。すると、彼女は顔を上げ、顔の前で手を振り返してくれた。
胸を高鳴らせている自分に赤面しているのが、頬の火照りでわかった。
▶次の話 見つめることや、知り合うことを|うさぎの耳〈第二話〉
◀前の話 夫は教職について七年ほどした頃、次第に心身をすり減らしていった|うさぎの耳〈第一話〉
谷村志穂●作家。北海道札幌市生まれ。北海道大学農学部卒業。出版社勤務を経て1990年に発表した『結婚しないかもしれない症候群』がベストセラーに。03年長編小説『海猫』で島清恋愛文学賞受賞。『余命』『いそぶえ』『大沼ワルツ』『半逆光』などの作品がある。映像化された作品も多い。
















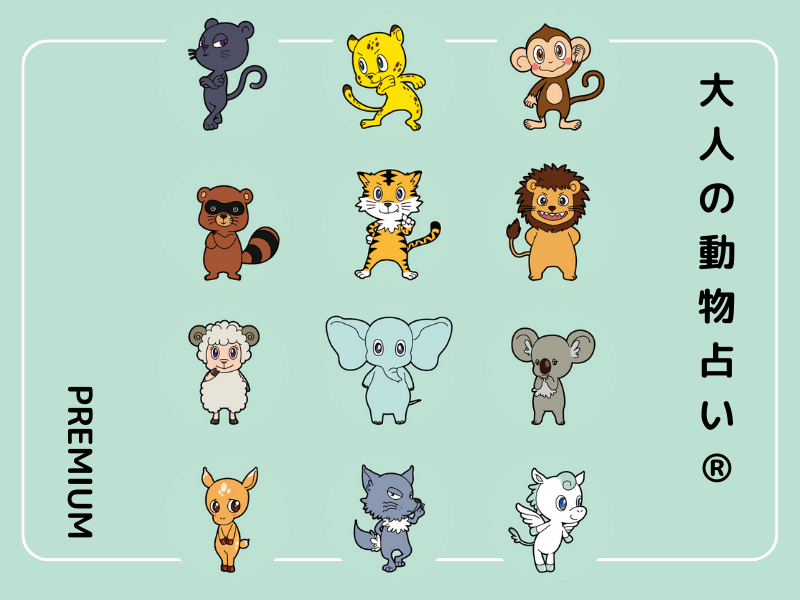




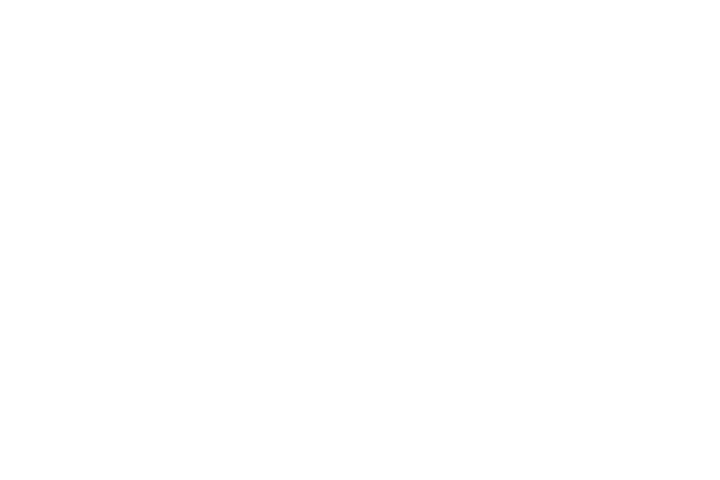
![[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひどい肌トラブルを救ってくれたのはコレでした」](http://img.kurashinista.jp/get/2025/11/26/93c18d7d3165c4c47e065f488a61a5ef.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...
[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...![[PR]体調による〈ゆらぎ肌〉に!「敏感肌フェイスケア」が頼れる理由](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/21443447263715306acb3453ec0366c1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]体調による〈ゆらぎ肌〉に!「敏感肌フェ...
[PR]体調による〈ゆらぎ肌〉に!「敏感肌フェ...![[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キッズ ベビーオリゴ®」が選ばれる理由とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2025/12/31/240a8d7521e72fb6ab5027cf72b2e102.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...
[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...![[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり・やわらか・伸び~る肌に!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/1649bec205350eddf0f29d2df2476ac8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...
[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...![[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う? 赤のジェリーでおなじみ「アスタリフト」たった7日試しただけで「わかったこと」とは!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/09/9baa7cd6aa648b5f68a397f6e1c292d8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...
[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...![[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝も、腹ペコな午後も。私たちが『超熟』を選ぶ理由って?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/26/d0a6213d838b9a06de95e683d0c14391.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...
[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...![[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家庭で効率よく向き合うケアアイテムが新登場!骨盤底筋専用EMS「SIXPAD ペリネフィット」](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/87aab1fc469c237111f888f1820fa561.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...
[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...![[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料理、ものづくり体験など魅力満載。【只見線】の旅の楽しみ方](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/6e401437f5ed3d32fe88e08a32f838e1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...
[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...















































コメント
全て既読にする
コメントがあるとここに表示されます