サクっと揚がった唐揚げやとんかつ、コロッケにドーナツと、魅惑の揚げものをするのに欠かせない揚げ油。
揚げ物に使う天ぷら油やサラダ油は、一体何回まで使いまわせるのでしょう?
「油が疲れる」と言うけれど、それはどういうこと?
などなど、揚げ油の酸化についてまとめました。
油の酸化とは?
前回と同じ油で揚げものをしたとき、臭いがしたり、粘り気が出てきたり、カニの泡のようなものが浮かんで消えにくくなったりしたことはありませんか?
これは、油が疲れている状態=酸化が進んでいるということです。
油が疲れる原因は、主に加熱による酸化です。
揚げ物をするときの温度は約180度。
調理中この高音に10分以上さらされ、そのあと冷めるまで空気に触れていれば、1度の使用でも酸化が進むのは当然です。
ただ、減った分を新しい油で補いながら3〜4回は使っている人も多いですし、
調理後の保管をきちんとすれば、その程度は問題がないと言っていいでしょう。
ただし、家庭で揚げ物をする頻度というのは、以前の調査で月平均2回だそう。
となると、1回目の使用と2回目の使用で2週間近く開くことになりますね。
油は長期にわたって保存していると、その過程で空気中の酸素や光、熱などの作用により酸化が進みます。
こうして、2週間に1度程度の使用を3、4回繰り返すと、油は酸化し、臭いを放ったり、味も劣化してしまうというわけです。
酸化した油のデメリットは?
酸化した油のデメリットは、その油で揚げた料理を食べたことによって起こる健康被害です。
急性のものとしては、下痢など引き起こすことがまれにあります。
長期的な視点で見ると、酸化した油は動脈硬化やがんの原因にもなるなどと言われています。
酸化した油が体に悪い理由は?
油の酸化も、少々臭いがする、仕上がりがべたつくなど、比較的小さな影響ならまだ良いのですが、
さらに酸化が進むとどうなるのでしょう?
動脈硬化の一因に?
油は過酸化脂質という物質を生成し始めるのですが、この過酸化脂質が動脈硬化を引き起こす一因ではと言われています。
肝臓への負担が増える
揚げ物に使われ、高温に加熱された油に、過酸化脂質という物質が含まれるのは前述の通りです。
そして、この過酸化脂質を分解できる臓器が肝臓。酸化した油で揚げたものを食べると、この過酸化脂質の摂取により、肝臓に負荷がかかってしまいます。
こういった食生活が長く続くと、肝機能障害や脂肪肝を引き起こす原因にもなると言われています。
酸化コレステロールの危険性
酸化コレステロールとは、食べ物に含まれる、質の悪いコレステロールのことです。
ファストフードのフライドポテトや焼き鳥の皮の部分などに多いもので、体内のLDLコレステロールを酸化させ、動脈硬化の一因にもなると言われます。
この酸化コレステロール、家庭での摂取の一番のリスクが古い油で揚げた揚げ物。
血管に悪影響を与え動脈硬化のリスクがある酸化コレステロール、なるべく体の中に入れたくないですね。
油が酸化する原因が知りたい!
油が酸化する主な原因は、光や熱です。
一度使用した油は「熱酸化」という現象が起きやすく、劣化が進んでしまいます。
熱は調理中の熱だけでなく、常温の室内で放置することも油をいためる原因に。
暑い季節には冷蔵庫での保管もおすすめです。
また直射日光はもちろん、蛍光灯などの光でも酸化は進みます。
空気に触れることでも酸化するので、保管にはきちんと蓋のできる容器を使いましょう。
酸化した油の見分け方は?
劣化した油は、色が変わり、ある種類の泡が立ち、臭いも変わってくるので、注意深く観察すれば、状態がよくわかります。
色の変化
何度も揚げ物をしているうちに、茶色くやや濁った色になり、鍋の底が見えないような状態になることがあります。
この状態で揚げ物をすると、食材の中まで火が通らないうちに、表面のみ焦げた色がつくことも。
またそれだけでなく、健康にも良くないので、このような状態の場合は処分して、新しい油を使いましょう。
泡
カニの泡のような細かく消えにくい泡が立っている場合、油は劣化しています。
シュワシュワとたくさんの泡が立ち、揚げている食材が見えないような状態になる場合は、油が相当疲れているので、使用をあきらめましょう。
泡と言っても、すぐに弾けて消える水蒸気の泡や、ぶくぶくと盛り上がる、消えにくい大きな泡は大丈夫。
大きな泡は、食材の中や、衣に含まれるレシチンという成分が油に溶けることによって発生するものです。
・臭い
前回揚げたものの臭いがするようなときや、かすかに焦げ臭かったり、揚げ物臭が強いときは、その油で調理をしても、おいしい仕上がりが期待できません。
こんなときは新しい油に交換したほうが良いでしょう。
・煙
油を火にかけたとき、食材を入れないうちから煙が立ちのぼるのは、油が劣化している状態です。
・粘り気
サラダ油は本来さらさらとしているもの。
保存容器から揚げ鍋へ油を移し替える際、とろりと粘り気のあるように感じたら、その時点で使用をストップしましょう。
油の正しい使い方、使用後の保存法は?
揚げ油の正しい使い方としてはひとつだけ、調理中、必要以上に熱して高音にしすぎないということです。
目安は180度前後で、鍋の中の温度が均一になるよう、即材を揚げている間もときどき菜箸などで混ぜます。
また、使用後はすぐに揚げカスを残らずすくって取ること。
少し冷めたら油こしきやこし紙(なければコーギーフィルターなどでも可)を使って、細かい揚げカスをさらに取り除き、油が完全に冷めたら蓋をして、保存容器で冷暗所に保存します。
この方法で保存すれば、3〜4回は繰り返して使っても問題ないはずです。
油こし器、保存容器のおすすめも2点、ご紹介しておきます。
野田琺瑯 オイルポット ロカポ/野田琺瑯
おしゃれで、キッチンのアクセントにもなるデザインが人気の、野田琺瑯制のオイルポット。
揚げ物に使った油を保存しても臭いがつきにくい素材で、油こしの部分には活性炭のフィルター付き。
油をより良い状態で保存できますね。
貝印 KAI オイルポット 1.2L 2重口 油だれ ストップ設計 テフロン セレクト DZ0709/貝印
昔ながらのシンプルなオイルポットですが、テフロン加工で汚れがつきにくくなっています。
油こし部分はシンプルなネット状で、洗いやすいのもポイント。1000円台で買える気軽さですが、容量も1.2ℓとたっぷり、注ぎ口が二重で油がこぼれにくいと、使い勝手の良い商品です。
油名人 F-600166/青芳
使いやすい小さめサイズの揚げ鍋と、こし器&保存容器が一体となったタイプ。
揚げ鍋の上部がややすぼまっているので、保存容器に被せるだけでピタッと蓋ができてしまうという完璧な設計。
毎朝のお弁当作りなどに、揚げ物を頻繁にする家庭にはぴったりです。
油の正しい捨て方は?
油の正しい捨て方は、自治体の指導によりますが、一般的には次のような方法があります。
・紙や布類に染み込ませて捨てる
温度が下がった油を、新聞紙やボロ布などを詰めた牛乳パックの空き容器に注ぎます。
最後は牛乳パックの口を粘着テープなどで閉じて、多くは燃えるごみとして捨てます。
自治体によって分別法が違う場合があるので、その場合は自治体の指示に従ってください。
場合によっては発火の危険があるので、高温の油を紙や布に染み込ませることのないようにしましょう。
ビニール袋を使って
穴があいていないしっかりしたビニール袋を大きめのボールや鍋などに広げ、新聞紙やボロ布を詰めて、そこに常温まで冷めた油を流します。
最後はビニール袋の口をしっかりとしばって捨てます。
この場合も条件によっては発火の危険があるので、高温の油を紙や布に染み込ませることのないようにしましょう。
・油処理剤で固めて
「固めるテンプル」などの廃油処理剤で固めて捨てるというのも一般的です。
この場合は、製品にもよりますが、凝固できる温度が決まっているので、油の温度を見極めて使用してください。
固めたあとは燃えるゴミとして捨てます。
・廃油回収に出す
自治体によっては、廃油を回収してリサイクルし、再資源化しているところもあります。
・手作り石鹸にリサイクル
揚げ物に使った油で、合成洗剤を含まない、自然派石鹸を作ることができます。
600ccの廃油から、通常サイズの石鹸が5~6個できるそうなので、試してみたいですね。
油が酸化しないようにする防止策は?
揚げ物をしたあとの油がなるべく酸化しないように良い状態をキープするためには、揚げ物をしたあとの鍋をそのままにしておくのはNG。
特に鉄製の鍋では酸化が進みやすくなるので、かならず油保存容器で保存します。
油を保存容器に移すときには、揚げ物をしたときに出た揚げカスなどを必ずこして、きれいな状態にすることが大事です。
揚げ物を終えたら、やけどに十分注意しながら、熱いうちに油こし器や目の細かいザルなどで油をこし、冷ましたあとに油の保存容器へ移します。
油の中に残った汚れが少ない場合は、底に残った揚げカスはそのままに、上澄だけを保存容器に移し替えても大丈夫です。
保存容器は光を通さず、蓋で密閉できるものを選びましょう。
冷めた状態で暗くてできるだけ涼しい場所に保存し、なるべく早めに使い切るようにしましょう。
参考:味の素ダイレクト https://ajinomoto-direct.shop
まとめ
処理が面倒な揚げ油ですが、かわいいオイルポットを買って保存し、3~4回の使用で処分、のサイクルで管理していけば、すっきりしてモチベーションも上がりそうですね。
きれいな油で、おいしい揚げ物を作っていきましょう。
文/伊波裕子














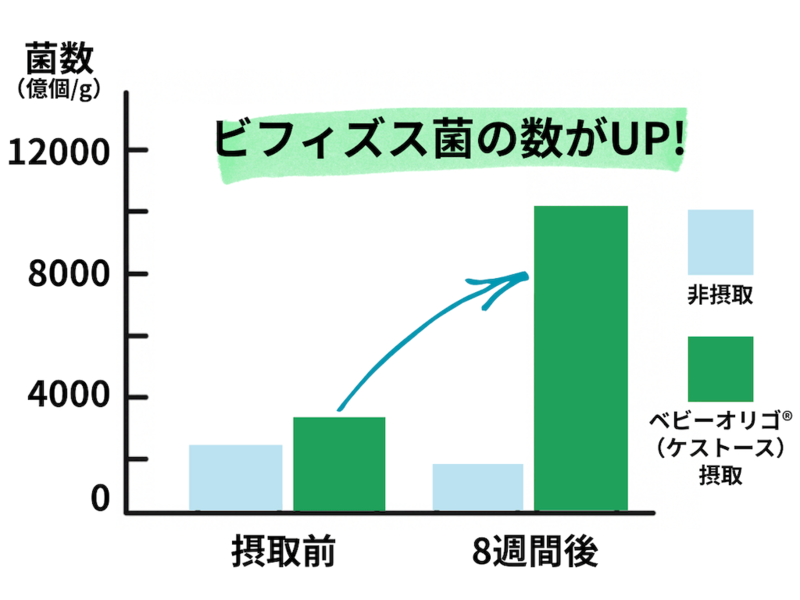

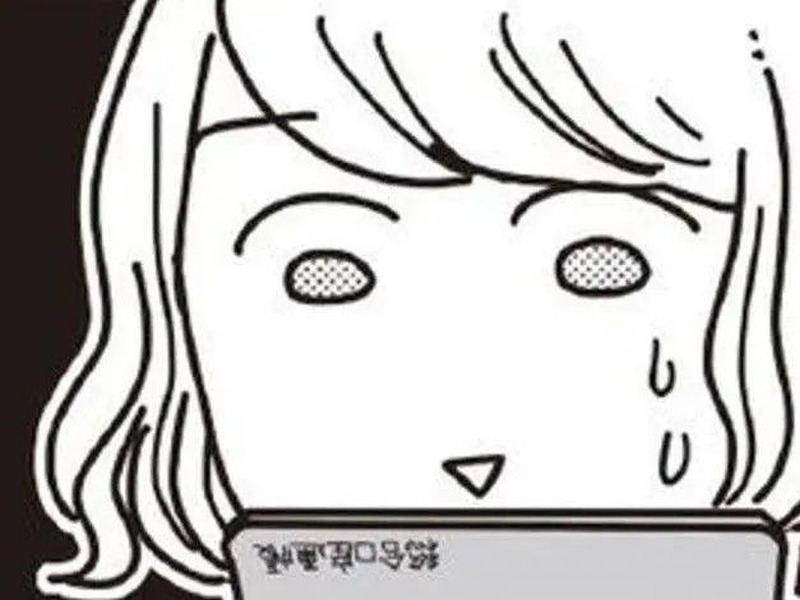



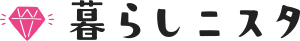


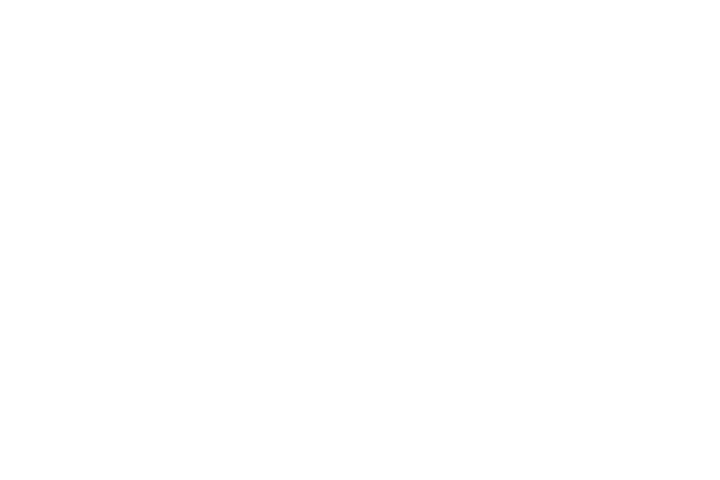

![[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝も、腹ペコな午後も。私たちが『超熟』を選ぶ理由って?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/11/1af31690c1712e58b0eab662d945ed3a.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...
[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...![[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひどい肌トラブルを救ってくれたのはコレでした」](http://img.kurashinista.jp/get/2025/11/26/93c18d7d3165c4c47e065f488a61a5ef.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...
[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...![[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベビーから大人まで使えるこのスキンケアの実力とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/652a60fa2cd3a587a9a42d7164dad1c1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...
[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...![[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キッズ ベビーオリゴ®」が選ばれる理由とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2025/12/31/240a8d7521e72fb6ab5027cf72b2e102.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...
[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...![[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり・やわらか・伸び~る肌に!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/1649bec205350eddf0f29d2df2476ac8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...
[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...![[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う? 赤のジェリーでおなじみ「アスタリフト」たった7日試しただけで「わかったこと」とは!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/09/9baa7cd6aa648b5f68a397f6e1c292d8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...
[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...![[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家庭で効率よく向き合うケアアイテムが新登場!骨盤底筋専用EMS「SIXPAD ペリネフィット」](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/87aab1fc469c237111f888f1820fa561.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...
[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...![[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料理、ものづくり体験など魅力満載。【只見線】の旅の楽しみ方](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/6e401437f5ed3d32fe88e08a32f838e1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...
[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

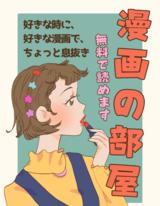














































コメント
全て既読にする
コメントがあるとここに表示されます