予想もできなかった「コロナ」を体験して、日々の生活や仕事、子どものことなど、誰しも少なからず影響を受けたのではないでしょうか。そして同時に、家族の健康や家計について、改めてしっかり考えるべきと思った人も多いはず。
そこで、子育て真っ最中の暮らしニスタユーザー5名に集まってもらい、座談会を開催。コロナ禍での体験や率直な気持ちを話していただき、これからの「ウィズコロナ」の暮らしに必要なことについて考えます。
コロナ禍の暮らし、変化や不安はあった?
集まってもらった5人のママたち、コロナ禍を経て家計に変化はあったのでしょうか。また、感染拡大中はどんなことに不安を感じていたのか、聞いてみました。
▲左から、もんでん ななさん(ライフオーガナイザー®︎。夫と中学生の長男、小学生の長女、幼稚園の次女の5人家族)、三木芽久美さん(クラフト作家、小学校の家庭科講師。夫と小学生の息子2人の4人家族)、nananamamaさん(介護職員。夫と小学生の娘の3人家族)
もんでんさん:ありがたいことに収入にコロナの影響はありませんでしたが、レジャー費が減った一方で食費が増えました。昨秋、子どものクラスメートがコロナに感染したときは、見えない恐怖を感じました…。
三木さん:家族でのお出かけや外食に敏感にならざるを得なかったので、やはり出費はその分減りました。夫は医療関係に勤めているので、いつ感染するかわからないという不安は常に抱いていましたね。
nananamamaさん:私の仕事は介護関係ですので、仕事で気を付けることは多かったですが、収入や生活面では食費が増えたくらいで変わりなく生活できました。
▲左から、野島ゆきえさん(フードコーディネーター。夫と12歳・10歳・2歳の息子と5人家族)、増田陽子さん(キッズ食育マスタートレーナー。夫、中学生の長男、小学生の次男の4人家族)
増田さん:子どもたちのサッカーの試合が減ったとはいえ、練習中にマスクをしないのも心配で…。もし家族が感染したら、私が仕事を休まなくてはいけないということも不安でした。
野島さん:食材費が増えましたが、外食をしなくなったので、プラスマイナスゼロでしょうか。
コロナの感染予防のため小さな子どもが触ったところは特に除菌をしっかりしなくてはと、ちょっと過敏になっていた気がします。
みなさん、コロナ感染拡大中はちょっと過敏になりながらも、家族の健康の大切さや、いざというときに備えられる家計の重要性を実感したようです。
心配ごとナンバーワンは「子ども」!
コロナをきっかけに、なんとなく抱えていた不安が浮き彫りになったという5人。中でも、子どもの成長にともなって増えていく食費や教育費については、ことさら心配なようです。そして、すべての土台は家族の健康!という認識も強くなったと言います。
野島さん:以前、子どもが怪我をしたとき、治療の実費を支払った後で学校の保険から戻ってきたとことがありました。男の子3人だと、これからも同じようなことが起きる可能性がありそうですよね…。
もんでんさん:最近は自転車事故のニュースを耳にすることが多いので、先日、子どもの自転車を買った際に自転車保険に入りました。これからかかってくる3人の子どもの教育費についても、正直不安です。
増田さん:コロナ以前のことですが、夫が網膜剥離になり入院・手術・自宅療養の日が続いたときは不安でした。コロナ後の将来も心配ですよね。
三木さん:夫が10歳年上ということもあり、先行きに漠然と不安を抱いています。最近は私自身もいろいろな不調を感じていて、ダンス教室や整体に通って心身をメンテナンスするよう心がけています。健康な体が生活の資本ですから!
nananamamaさん:みなさんと同じように、私も子どもの教育費と夫婦の老後資金はしっかり備えたいと思っています。そのためにも、家族が健康であることは不可欠ですよね。
コロナ禍では家計への直接的なダメージこそありませんでしたが、子育てど真ん中の世代にとっては、子どもに関するケガやトラブル、将来的な家族の健康や家計に対する不安は膨らみがちのようです。
保険や保障はどうしてる?
コロナに限らず、病気やケガのときに経済面でも精神面でも支えてくれるのが保険ですが、5人は、保険や保障についてどんなふうに考え、具体的にはどんな備えをしているのでしょう。
三木さん:子どもたちの学資保険と私たち夫婦の医療保険、夫の収入保障保険に加入しています。
私は20歳のときに病気をしたのを機に医療保険に入ったのですが、最近、内容を見直したら保険料が倍になっちゃいました。毎月、かなりの額の保険料を払っていて、負担に感じているんですよね…。
nananamamaさん:わが家も、子どもは学資保険に、夫は医療保険と死亡保険に入っています。夫は、義母がかけていた都民共済に結婚後も継続して入っています。私も以前はネット保険に入っていたのですが、直接相談しづらいのが気になって解約してしまいました。
もんでんさん:結婚を機に、夫婦で医療保険と死亡保険に入って、夫が病気になった折に保険のお世話になりました。そこで初めて、「保険ってやっぱり役に立つんだな」と実感しました。
とはいえ、子どもの医療費は、今は自治体の助成で間に合っているし、いつどんな保険をかけるべきかはよくわからないままです。
増田さん:お恥ずかしいのですが、うちはどんな保険に加入しているのか把握できていなくて(苦笑)、これを機に確認しました。医療保険、死亡保険、介護保険に夫婦とも入っていました。とはいえ、コロナに感染したときにも保障はあるのかなど、“今”に適しているのかどうかはよくわかりません。
野島さん:夫は医療保険、死亡保険に入っていますが、内容はよくわかっていません。子どもの学資保険も入ろうかと思ったのですが、結局は、それぞれ銀行口座を作って積み立てています。
私は保険に入っていないので、そろそろ検討しなきゃと思うのですが、「女性特約?」「この小さい文字の説明を全部読むの?」「これとこれは何が違うの!?」と聞けば聞くほど思考が止まってしまって…。
保険に入ってはいるものの、「今の保険でいいの?」「実はよくわからないまま加入している…」というのが実情のよう。たしかに保険商品は仕組みが複雑。必要性は感じつつも、決定は後回しにしてしまっているという人も多いのではないでしょうか。
そんな方にぴったりの、『都民共済』という選択肢があるのをご存知ですか?
都民共済とは? 顧客満足度第1位(※)の理由にナットク!
保険・保障といえば…パンフレットやホームページには細かい文字や数字がズラリ。会社や商品をいろいろ比較してみてもいまいちピンとこず、結果、加入までの道のりが遠のいてしまいがちですが、シンプルでわかりやすい!と評価が高いのが『都民共済』なんです。
ここからは都民共済の職員さんにも座談会に加わっていただき、加入者の満足度が高い理由を教えてもらいました!
※2020年度 JCSI(日本版顧客満足度指数)調査 生命保険部門
掛金は月々2,000円~だから、負担が軽い!
都民共済・村田さん(写真右):おそらく、みなさんが特に気になるのは、毎月の掛金(保険料)ではないでしょうか。
18歳から加入できる生命共済の掛金は、年齢を問わず(※)基本的に月々2,000円。掛金の端数なしの明瞭さは「わかりやすい!」とご好評いただいています。
「総合保障型」では死亡保障も充実しており、「入院保障型」では入院1日目から10,000円の保障が受けられます。もちろん、どちらも先進医療の保障が含まれています。
※60歳以降は、年齢区分に応じて保障内容が変わります。
「割戻金(わりもどしきん)」でちょっぴりお得気分♪
都民共済・多田さん(写真左):『都民共済』は非営利の生活協同組合ですので、助け合いの精神が根底にあります。その特長のひとつが「割戻金」です。決算後に剰余金が生じた場合、ご加入者さまに「割戻金」としてお戻ししているんです。
「総合保障型・入院保障型」の場合では払込掛金の39.77%(※)をお戻ししています。例えば、年間24,000円の掛金を払っても、後から9,544円が戻ってくる計算になります。これは、私たちも誇りに思っていて、加入者さまにも喜んでいただいているポイントです!
※都民共済 割戻率実績(令和2年度)39.77%(3月31日現在のご加入者を対象に、8月に掛金振替口座へお振り込み)
※割戻金は、共済金のお支払い等による剰余金の増減で変動します。
※割戻金の中から一定割合を財務基盤の強化を図るため、総代会決議により、出資金に振替ることをお願いしています(こども型は除く)。ただし、毎事業年度の割戻率の状況等により振替を行わない場合があります。なお、組合を脱退するときは、出資金返還手続きをおとりいただきます。
共済金の支払いスピードが早い!
都民共済・村田さん:共済金を迅速にお支払いすることにも力を入れています。加入者さまが発送した請求書類を少しでも早く処理するために、職員が郵便局へ取りに行くんです。なるべくその日のうちに口座へお振込できるよう努めています!
子育てファミリー向けのコースも充実
都民共済・多田さん:子育て中のみなさまには、0歳から満17歳まで加入できる「こども型」をおすすめします。掛金は月々1,000円または2,000円の2コースがあり、どちらも入院やケガの通院が1日目から保障されます。
私も子どもが3人いるのですが、子どもが入院・通院するとなると、親は仕事を中断して駆けつけますし、付き添いやタクシー移動などが必要なケースも多く、医療費以外の出費が意外とかさむんです。自治体によっては子どもの医療費はかかりませんが、それ以外のサポートで『都民共済』がお役に立てると思います。
都内在住者だけじゃない!都内勤務でも加入OK
都民共済・村田さん:『都民共済』という名称なので、東京都にお住まいの方しか加入できないと思う方も多いようですが、東京にお勤めの方もご加入いただけます。実際、埼玉や神奈川など東京近県にお住まいの方にもたくさんご加入いただいています。
「仕組みがわかりづらい」「毎月の掛金が負担…」などの心配は、『都民共済』なら払拭できそう!と感心したり、ホッとしたりしながら説明に耳を傾けていた5人。聞くほどにそれぞれ気になる点が出てきたようで、ここから質問タイムです!
令和3年7月の時点で、加入件数が212万件という『都民共済』。東京都のおよそ8人に1人が加入している計算になるという、その圧倒的信頼度の理由がわかりました。5人のママたち、質問が止まりません!
「自転車保険はついていないのですか?」
都民共済・村田さん:事故の場合、お子さまのケガはもちろん、相手に対しての補償も気になります。『都民共済』は損保ジャパンさまと提携していて、「個人賠償責任保険」もご用意しています。年間1,680円の掛金で、最高3億円までの賠償補償がついています。
自転車での加害事故の場合も対象となるので、お子さまの自転車保険としてもご利用いただけます。1人が加入すれば家族全員をカバーできるので、とても心強いのではないでしょうか。
「過去の通院についても請求できますか?」
都民共済・多田さん:はい!請求期限は3年ですので、その期限内で通院を証明できるものをご用意いただければ大丈夫です。そのときはバタバタして請求できていなかった場合も、ご安心ください!
「民間の保険会社と『都民共済』の違いはなんですか?」
都民共済・村田さん:よくある例えでは「保険会社はタクシーで、共済はバス」と言われます。タクシーは個々の要望に合わせて行く先が決まるので、その分料金が高めですが、バスは一律の安価な料金でどなたでも乗ることができますが、到着場所はバス停に決められていますよね。こうイメージしていただくと、保険会社さんと『都民共済』の特長の違いがわかりやすいのではないでしょうか。
「『都民共済』に家族割はありますか?」
都民共済・村田さん:残念ながら家族割はないのですが、ご加入者さま限定のお得なサービスをいろいろご用意しています。結婚式の衣装レンタルや挙式プラン、スーツのお仕立てや成人式用振袖販売会、雛人形展示販売会など、ご家族の大切な記念にご利用いただけるサービスが多く、このためにご加入される方もいらっしゃるんですよ。
「保険料の負担、軽減できますか?」
都民共済・多田さん:「毎月の保険料で家計が圧迫されている」と感じた時点で見直しが必要かもしれません。とはいえ、お客さまそれぞれの状況・事情がありますから、まずは『都民共済』の普及スタッフにお気軽にご相談ください。重視したいこと、気になる点などをお話しいただければ、納得いく保障にたどり着けるようサポートいたします!
保険・保障選び、一歩踏み出すきっかけに♪
「こんなこと誰に聞けばいいの…?」というママたちの不安や疑問がクリアになって大いに盛り上がった座談会。都民共済職員さんのわかりやすい説明を通じて、5人の考えや気持ちには変化があったようです。
もんでんさん:今日はいろいろ勉強になりました!職員さんのお話がわかりやすく、「みなさん、誠実だなー」という印象を持ちました。「割戻金」はとても魅力に感じたので、夫とも相談して家族全員の保障を見直そうと思います。
三木さん:目からウロコのお話をたくさん聞かせていただき、「もしかしたら保険料の負担が減らせるかもしれない!」と思えました。加入者特典も実はいろいろあると知って、『都民共済』を選択肢に加え、家計全体の掛金の割合を低くしたいと思います。
nananamamaさん:『都民共済』は掛け捨てだと思っていましたが、割戻金があることを知って「私も入ろう!」と思いました。自転車保険など子どものいろいろなトラブルにも対応できるのは心強いですね。
増田さん:初めて知ることばかりで、特に、年齢が上がっても掛金は上がらないことや割戻金制度が印象的でした。今まで、苦手意識があって考えるのを避けていた保険のことを、ちゃんと考えて見直すきっかけとなり、今日は参加してよかったです!
野島さん:ときどき目にする『都民共済』のチラシ。しっかり読む機会がなかったのですが、職員さんから直接話を聞けて勉強になりました。特に、共済と保険の違い、この2つを組み合わせるメリットが見えて、保険を検討したり決めたりするハードルが下がりました。ありがとうございます!
ウィズコロナ時代。家族の保険・保障は『都民共済』がおすすめ♪
仕組みがシンプルで、月々の掛金が一律、おまけに、うれしい「割戻金」がある『都民共済』。
万が一、コロナに感染した場合の保障も備えている安心感も、今の時代にマッチしますよね。「今の保険で大丈夫かな」「家族の保障を見直さなきゃ」と考えている人は、まずは『都民共済』の詳細をチェックすることからはじめてみては!
提供/東京都民共済生活協同組合
写真/畠山あかり、文/みやご かよ
※撮影時のみマスクを外しております。


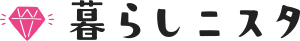


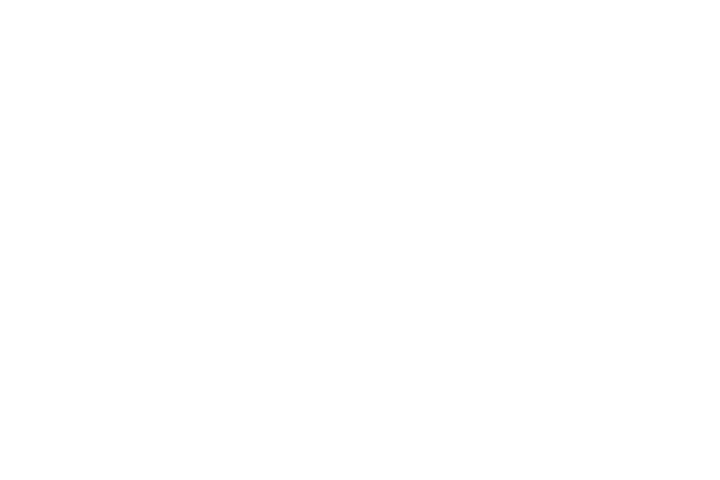
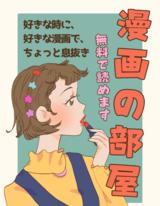










































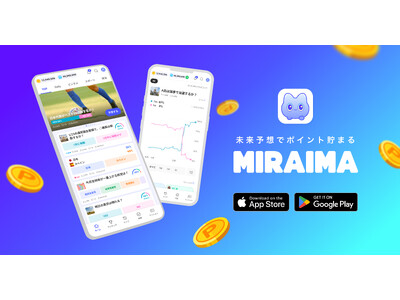

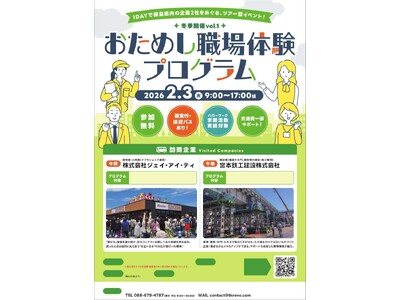
コメント
全て既読にする
コメントがあるとここに表示されます