学校や職場、レジャーまで、いろいろなシーンで活躍するステンレスの水筒。季節ごとに温かいもの冷たいものと好きなドリンクを持ち歩くのに便利なので、最近はどこへ行くにもマイボトルを持参しているという方も多いようです。
そんな毎日の生活に欠かせない水筒、正しい方法で洗っていますか?
つい面倒でサッと水洗いで済ませたくなるなりがちですが、気付かないうちに黒カビなどの汚れがたまっていること、ありますよね。水筒は、ちょっとの工夫で簡単に、綺麗に洗うことができるんです。お気に入りの水筒を長く愛用するためのお手入れ方法を紹介します。
水筒の毎日の手入れ方法が知りたい
水筒は日常的に使うものだからこそ、清潔な状態で使いたいもの。汚れを放置していると、菌やカビが発生して食中毒をひきおこす原因にもなりかねません。
しかし、毎日家族の人数分の水筒が台所にずらりと並ぶと、洗い物の多い日などは特に洗うのが面倒。最近ではシュッとスプレーするだけで汚れが落ちるという商品もありますが、毎日使うとなると案外高くついてしまいますよね。簡単に、経済的にお手入れできる方法をマスターしましょう。
準備するもの
毎日のお手入れに必要なものは3つです。
【準備するもの】
1.台所用中性洗剤:汚れ落ちがよく、できれば香りの強くないもの
2.柄つきスポンジ:やわらかくて水筒本体の口に入る大きさ、底に届く長さのもの
3.食器用スポンジ:普段食器を洗うときに使っているもの
【手順】
1.水筒を分解する
本体、蓋、中栓、パッキンといった部品を外し、バラバラにします。
2.水洗いする
本体に水をいれ軽くすすぎます。
3.台所用中性洗剤を使って洗う
柄のついたスポンジに洗剤を2、3滴たらし、本体の中、底部分にあて、柄の部分をまわしながら洗います。本体の口、蓋、パッキンは洗剤をつけた食器用スポンジで丁寧に洗います。
4.すすいで乾かす
本体の中、複雑な形状の蓋の中、パッキンを洗剤の泡が残らないように丁寧にすすぎます。ぬるま湯を使うと水切れがよく、乾きやすいのでオススメ。本体の外側の水気は水あとが残らないようにふきとり、中の水気をしっかりと切って完全に乾かします。
水筒を洗うのに、あると便利な道具は?
水筒を簡単にキレイにできる便利グッズが100円ショップにたくさんあります。その中でも特に便利なアイテムを紹介しましょう。
柄つきスポンジ
手の届きにくい、水筒の底や内側を洗うときに便利なのが柄つきスポンジです。柄の部分をフックにかけられるものが多く、柄の長さ、スポンジの大きさややわらかさ、材質などいろいろなものがあるので、お持ちの水筒に合ったものを選ぶといいでしょう。
スポンジの取り換えができて衛生的に使えるスポンジトングも便利。こちらも100円ショップで購入可能です。
柄つきスポンジは、キッチンにあるもので簡単に作ることもできます。作り方を紹介します。
【準備するもの】
菜箸2本
食器用スポンジ
輪ゴム2本
【作り方】
1.スポンジを縦長におき、上2㎝ほどを残し、手持ちの部分をゴムで固定した菜箸で両面から挟みます。
2.箸で挟んだスポンジの下から3分の1くらいの部分を、ゴムでしっかりと固定すれば完成です。
スポンジの代わりに、アクリル毛糸を巻きつけたものなども細かいパーツを洗うのに便利です。
ボトル用水切り
水筒を乾かすとき、本数が増えてくると場所をとりますよね。布巾に乗せて立てておくのも不安定ですし、水切りかごの中にいれると邪魔になることも。そんなときには「ボトル用水切り」が便利です。
棒に水筒を差して立てておくことができるので、倒れたりする心配もありません。水切りかごの縁に引っ掛けるフックタイプなら、フックにボトルの口を掛けて乾かせるので、場所もとらず、水が下のシンクに直接落ちるのでスッキリ!同じ引っ掛けるタイプで、蓋や中栓を置くアイテムもあるのでぜひチェックしてみてください。
細かい部分が洗えるミニブラシ
蓋の溝や飲み口など、洗いにくいところには専用のブラシが便利。溝から汚れを掻き出してくれるミニブラシや、ストロー洗い用の細いブラシなどを使うとキレイに洗うことができます。
水筒のNGな洗い方を知りたい
水筒は日常的に使うものだからこそ清潔にしておきたいもの。でも間違ったお手入れが食中毒や破損につながることもあるんです。やってはいけない水筒の洗い方を教えます。
金たわしでのこすり洗い
金たわしを使って水筒をこすってしまうと、表面を傷つけるだけでなく、水筒内部に見えない小さな傷がついて錆びてしまったり、そこから雑菌が繁殖する可能性もあります。水筒そのものの金属成分などが溶け出し、飲み物と一緒に口に入ってしまうこともありますので注意が必要です。
ゴシゴシ洗い
スポンジで必要以上に強くこすることもやめましょう。スポンジの硬いほうなどは、ステンレス製であっても水筒の中に小さな傷をつけてしまいます。優しく洗うようにしましょう。
クレンザーや重曹でのこすり洗い
茶渋やコーヒーの色などがこびりついていると、ついついクレンザーや重曹でこすり落とししたくなりますが、これはNG。これらには研磨剤が入っているので、内部のステンレスに細かい傷がついてしまいます。
食洗機(熱湯)での洗浄
水筒を熱湯や高温のお湯で洗浄する食器洗浄機で洗うと、変形してしまったり塗装がはがれたりして中身が漏れやすくなってしまうことがあります。水筒本体の塗装がはがれてしまうなど水筒を劣化される恐れもありますので、避けるようにしましょう。
塩素系漂白剤での洗浄
塩素系漂白剤の使用はさけましょう。塩素系の漂白剤には強い漂白効果がありますが、ステンレスや内側のメッキがはがれ、さびの原因となったり、水筒の保温・保冷機能の低下にもつながってしまいます。
しぶとい汚れを落とす方法が知りたい
毎日洗っていても、長く使い続けているうちに臭いや茶渋が気になってきます。汚れに気付かず使用を続けてしまうと、知らず知らずのうちにカビが大繁殖!なんてことにもなりかねません。
カビがついていた飲み物を飲んだからといって人体に影響があることはありませんが、体調不良で抵抗力が落ちているときや小さなお子さんには注意が必要です。
水筒をキレイに保つためには、毎日のお手入れのほかに、1週間に1度程度の時間をかけた丁寧なお手入れがオススメ。その方法を見ていきましょう。
酵素系漂白剤でつけ置き洗い
ステンレス製の水筒に塩素系の漂白剤はNGですが、酵素系はOK。つけ置きしてから洗浄します。
【準備するもの】
酵素系漂白剤
お湯
つけ置き用の容器
【手順】
1.水筒を分解する
本体、蓋、中栓、パッキンを外し、バラバラにします。
2.つけ置き用洗浄液を作る
つけ置き用容器に、お湯(30~50℃程度のぬるま湯)500mlと酵素系漂白剤小さじ1杯弱を入れ、混ぜます。
塩素系漂白剤と間違えないように気を付けてくださいね。
3.分解した水筒を洗浄液に浸す
本体以外の部品は2の洗浄液に浸します。本体は全体を浸さず、洗浄液を内部に入れます。それぞれ30分~1時間放置。本体に洗浄液を入れるときには蓋を閉めないようにしましょう。蓋をしたままつけ置きすると内部の圧力が上がってしまい、蓋が飛び出す危険性があります。また、あまり長くつけ置きするとゴムパッキンの劣化などに繋がりますので、長時間放置しないように気を付けてください。
4.しっかり洗い流して乾燥させる
水かぬるま湯で洗浄液を洗い流し、乾燥させます。
酢、クエン酸を使う
酢やクエン酸でも汚れが落とせます。特に白っぽい水アカ汚れなどはすっきりキレイになります。食材としても使用されているので、より安心して洗浄できますね。
【準備するもの】
酢、またはクエン酸
お湯
漬け置き用の容器
【手順】
1.水筒を分解する
本体、蓋、中栓、パッキンを外し、バラバラにします。
2.つけ置き用洗浄液を作る
つけ置き用容器に、お湯(30~50度程度のぬるま湯)と酢、もしくはクエン酸を10:1の割合で入れます
3.分解した水筒を洗浄液に浸す
1でバラバラにした部品を全て洗浄液に浸します。
4.しっかり洗い流して乾燥させる
水かぬるま湯で洗浄液を洗い流し、乾燥させます。酢の洗い流しがあるとカビの餌になってしまいますので、しっかりと洗い落としましょう。
卵の殻を使う
なかなか取れない水筒の底についた汚れなどは、なんと卵の殻でキレイに落とせます。卵の殻には漂白作用があるので、洗剤を使わなくても汚れが落ちるのだそう。
【準備するもの】
卵の殻
ビニール袋やジップロックなどの袋
お湯
【手順】
1.卵の殻を袋に入れて、粉々に砕く
全部細かく砕かなくてもOK。粗いものが混ざっていても問題ありません。
2.砕いた卵の殻を袋から水筒の中に入れる
こぼれないように気を付けて、卵の殻を水筒の中に入れます。
3.水筒にぬるま湯を入れる
水でも大丈夫ですが、ぬるま湯の方が効果が高まります。水筒の3分の1位まで入れてください。
4.水筒の蓋を閉めて振る
しっかり蓋を閉めて、水筒をシャカシャカと1分ほど振ります。
5.水筒をすすぐ
卵の殻が中に残らないよう、しっかりすすいでから乾燥させます。
部分別の洗い方を知りたい
つけ置きしても、蓋の裏側やゴムパッキンにこびりついた汚れや匂いが落ち切らないこともありますよね。水筒のパーツ別に、よりキレイに洗浄する方法を紹介します。
本体の洗い方
茶渋や匂いが落ちない時には、重曹での洗浄がオススメ。こすり洗いはNGですが、つけ置きするとキレイにとれます。
【準備するもの】
1.重層 100円ショップなどで購入できるもので可
2.お湯
【手順】
1. 熱めのお湯を水筒にいれる
60℃ぐらいの熱めのお湯を水筒の8分目~9分目まで入れます。重曹をお湯に溶かすと少量の炭酸ガスが発生するため、お湯が泡立って吹き出してしまうことがあります。そのため、お湯を入れる際には満杯にせず、余裕を残して入れるようにしてください。
2.水筒の中に重曹を小さじ1程度入れる
汚れが気になる場合は大さじ1くらい入れてもOK。クエン酸を加えるとより洗浄力が強まります。
3.水筒の蓋をして振り、そのまま漬け置きする
蓋をしっかり閉めて軽く振り、そのまま1時間ほどつけ置きします。
4.しっかり洗い流して乾燥させる
水かぬるま湯で洗浄液を洗い流し、乾燥させます。重曹水は弱アルカリ性になっているので、肌につくと荒れる場合もあるので注意が必要です。ゴム手袋をすると安心です。
中栓・ゴムパッキンの洗い方
形が複雑で洗いにくい中栓やゴムパッキンは、重曹水で洗うと汚れが落ちやすくなります。
【準備するもの】
重層(100円ショップなどで購入できるもので可)
お湯
保存容器、もしくはジップロックなどの保存用袋
【手順】
1.水筒を分解する
本体、蓋、中栓、パッキンを外し、バラバラにします。
2.つけ置き用洗浄液を作る
お湯(30~50℃度程度のぬるま湯)500mlに重曹を大さじ1入れて良く溶かします。
3.洗浄液と中栓、パッキンを保存容器、またはジップロックに入れる
2の洗浄液と、分解した中栓、ゴムパッキンを一緒に容器にいれ、しばらく漬け置きます。
4.振り洗いする
3をしっかり密封して振り洗いします。洗浄液がこぼれないように注意してください。
5.しっかり洗い流して乾燥させる
水かぬるま湯で洗浄液を洗い流し、乾燥させます。
中栓の細かい溝の汚れが落ち切らない場合は、綿棒や爪楊枝を使ってこするとスッキリ落ちます。
ゴムパッキンの洗い方
特に汚れがたまりやすく、カビもつきやすいゴムパッキン。毎日取り外して洗浄しましょう。
【準備するもの】
台所用中性洗剤
食器用スポンジもしくはメラミンスポンジ
【手順】
1.蓋から取り外す
手で外しにくい場合は、専用の小さいヘラなどを使って外すこともできます。
2.スポンジで洗う
食器洗い用のスポンジに台所用中性洗剤をつけ、洗浄します。通常のスポンジでも大丈夫ですが、毎日しっかり洗いたいならメラミンスポンジがおすすめ。お湯だけで軽くこするだけで汚れが落とせます。その後、洗剤を使って軽く洗えば清潔を保てます。
3.しっかり洗い流して乾燥させる
水かぬるま湯で洗い流したら、しっかり乾燥させてから蓋に装着しましょう。水切りかごに入れてしまうとかごの下に落ちたりしがちですので、清潔な布やペーパーでふき取り、その上に置いて乾かすといいでしょう。
もしパッキンにカビが生えていたら、洗っても再びカビが生えてくることがあります。劣化も進んでいる可能性が高いので、その場合は新しいパッキンに交換しましょう。1年に一回の交換が目安です。
蓋の洗い方
水筒の内側に比べて見落としがちな蓋にも、汚れがたまっています。クエン酸を使ってつけ置き洗いをすると汚れがキレイになります。
【準備するもの】
酢、またはクエン酸
お湯
つけ置き用の容器
【手順】
1.水筒を分解する
本体、蓋、中栓、パッキンを外し、バラバラにします。
2.つけ置き用洗浄液を作る
つけ置き用の容器にお湯(30~50℃程度のぬるま湯)1リットル、クエン酸を大さじ1~2ほど入れる
3.分解した蓋を洗浄液に浸す
蓋を2の洗浄液に2時間ほど漬け置きします。
4.しっかり洗い流して乾燥させる
水かぬるま湯で洗い流したら、しっかり乾燥させて元に戻しましょう。
まとめ
日々のお手入れの仕方から定期的に行いたいスペシャルお手入れまで、いろいろな水筒の洗い方があることがわかりました。毎日使う水筒なので、安心して使うためにも「使い終わったら洗う」ことが大切!中身を入れたまま放置したりせず、毎日しっかりキレイに洗って清潔に使ってくださいね。
文/田代智美














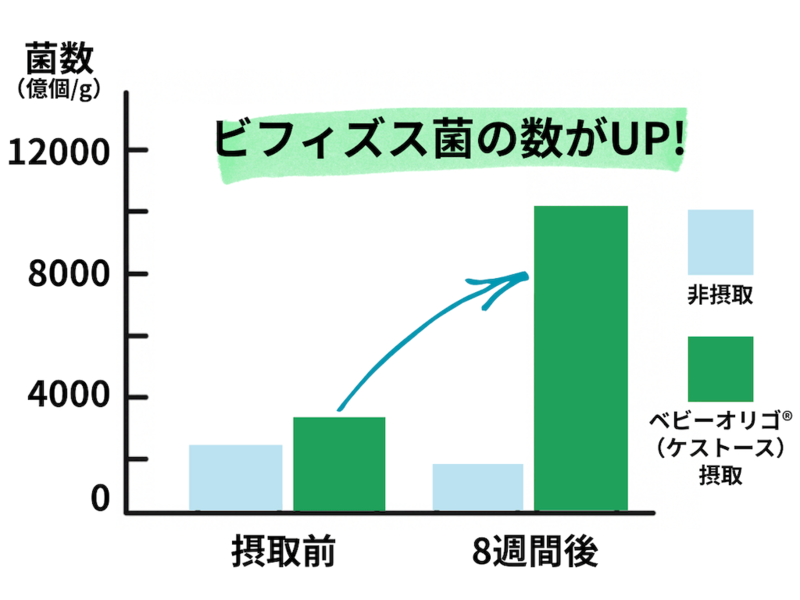

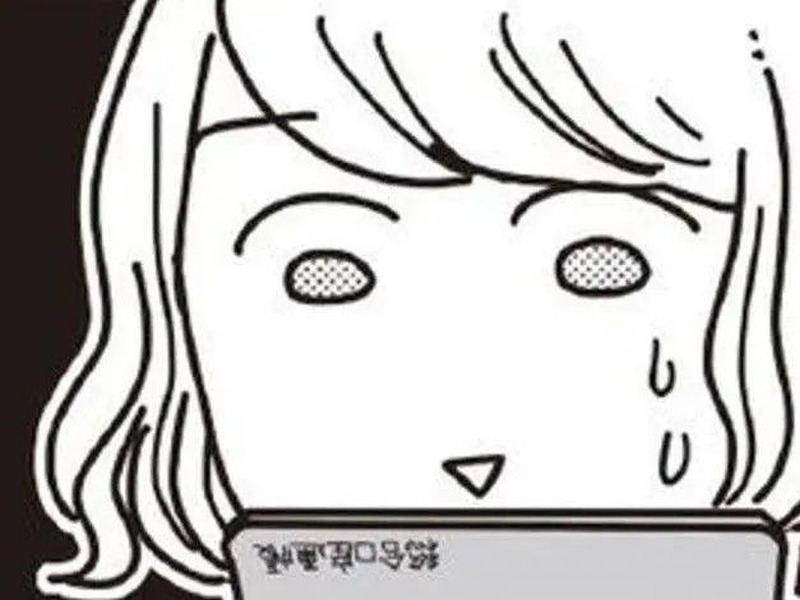



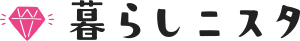



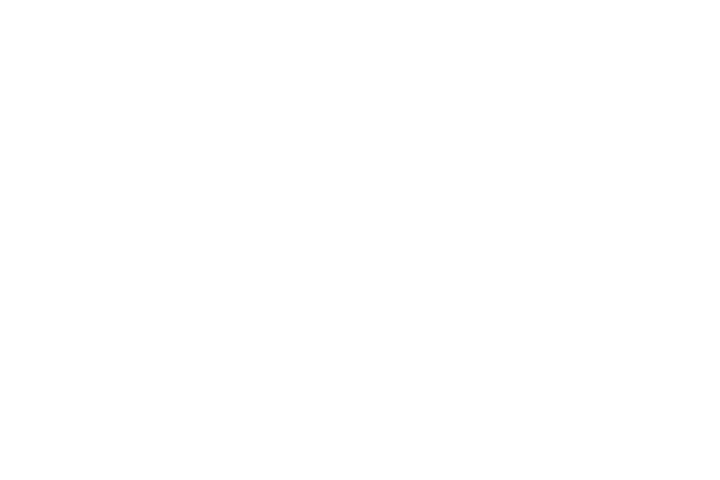
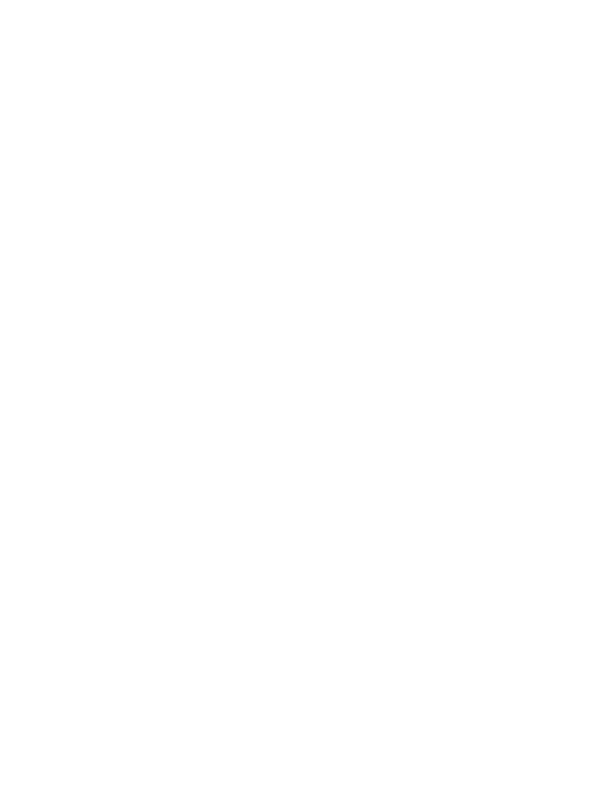
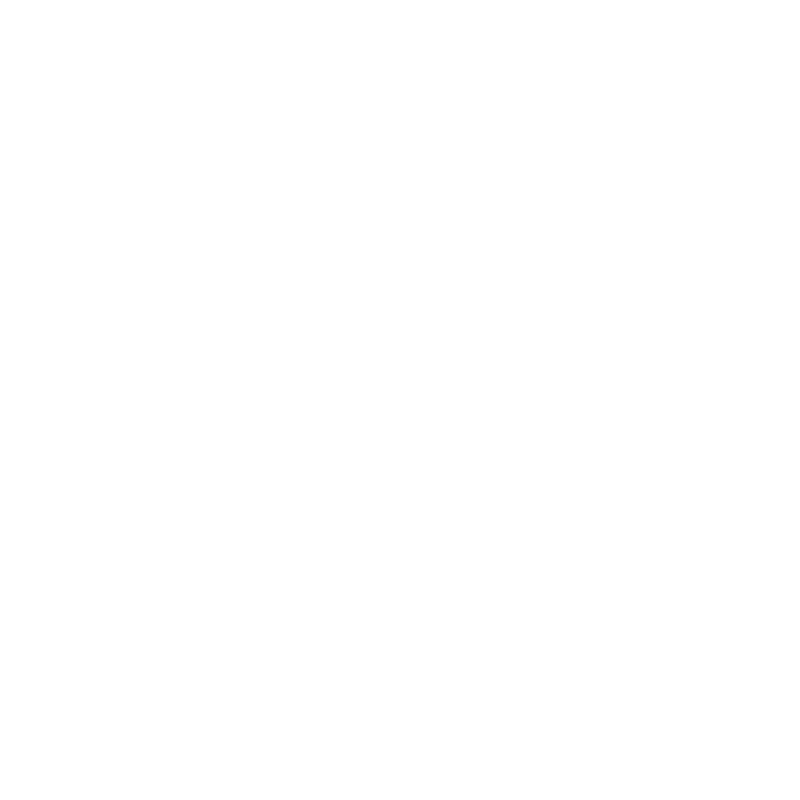
![[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝も、腹ペコな午後も。私たちが『超熟』を選ぶ理由って?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/11/1af31690c1712e58b0eab662d945ed3a.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...
[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...![[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひどい肌トラブルを救ってくれたのはコレでした」](http://img.kurashinista.jp/get/2025/11/26/93c18d7d3165c4c47e065f488a61a5ef.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...
[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...![[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベビーから大人まで使えるこのスキンケアの実力とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/652a60fa2cd3a587a9a42d7164dad1c1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...
[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...![[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キッズ ベビーオリゴ®」が選ばれる理由とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2025/12/31/240a8d7521e72fb6ab5027cf72b2e102.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...
[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...![[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり・やわらか・伸び~る肌に!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/1649bec205350eddf0f29d2df2476ac8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...
[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...![[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う? 赤のジェリーでおなじみ「アスタリフト」たった7日試しただけで「わかったこと」とは!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/09/9baa7cd6aa648b5f68a397f6e1c292d8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...
[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...![[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家庭で効率よく向き合うケアアイテムが新登場!骨盤底筋専用EMS「SIXPAD ペリネフィット」](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/87aab1fc469c237111f888f1820fa561.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...
[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...![[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料理、ものづくり体験など魅力満載。【只見線】の旅の楽しみ方](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/6e401437f5ed3d32fe88e08a32f838e1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...
[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

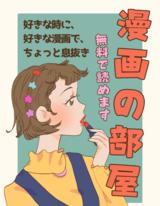














































コメント
全て既読にする
コメントがあるとここに表示されます