
◀初めから読む 母子の部屋は、一階にあるその角部屋である|うさぎの耳〈第一話〉
二階の窓は広く、厚地のカーテンを両端に手繰り寄せていくと一気に視界が開ける。朝ごとに、新しい一日の始まりを感じる。
陽射しがあれば、ベッドの上の白いシーツには、光がさまざまな線で形を描く。
ここ最近は、ずっと雨の日が続いている。庭に植えられた常緑樹は、夜通し待ってくれていたように雨粒に打たれながら、朝の挨拶をしてくれる。モクレンの樹は、タイサンボクというのだと、義母が友人に得意気に話していたから覚えている。この白い花は、樹木の上の方にだけたくさん花をつけるから、角部屋からはよく見えていなかったけれど、開花の時期からよく香っていた。確か、マグノリアと呼ばれて香料にもなるはずだ。この白い花も、落ちずに耐えている。
今日は久しぶりに雨が上がった。快晴だ。
理玖と私は、今週から、一階の角部屋ではなく、誰も使っていなかった二階の部屋の間借り人になった。格上げになったのだ。
ふた間続きで、ひと部屋は寝室。壁際には古めかしい彫刻のされた鏡台が備えられてある。ベッドは、シングルが二つ、ゆったりと幅を取って置かれている。
理玖が早く寝ついた日には、私はもう一つのベッドに座って、編み物をしたり、本を読んだりもできる。
身長も体重も増えた理玖が、頭の上に両手をあげて寝息を立てている姿を、もうひとつのベッドから眺める幸せが増えた。
莉子を招いた日の夜に、義母とこの「生活改善」のための話し合いは始まった。その晩、義母は、非常に不愉快そうに、私の約束違反をまくし立てた。私の方も、気づけば必死に反論していた。
その翌日からは口も利いてくれなくなったが、義母の方こそ、角部屋に私たちを閉じ込めていることに疲れていたのかもしれない。
「ちょっと来て」
先週になり、そう呼ばれて二階について上がった。
「ここでいいなら、使ったら」
「いいも何も、広々しています」
私の返事に、鼻を鳴らした。
「あなたね、だから、ありがとうって、素直に言えばいいんじゃないの?」
義母の口調には、いつもの刺々しさがあった。けれど、彼女の言う通りだとも思っていた。わかってはいるけれど、自分なら、こんな仕打ちをするだろうかとつい考えてしまうから、私の言葉にも刺がある。階段を上がったすぐ先に、こんなに広々した部屋が空いていたのなら、なぜ最初から貸してくれなかったのだろう。
「盗人猛々しい」と、先日義母から向けられた通りの気持ちが、この時も私には湧いていた。
「約束事は変わらず守ってちょうだいね。この間みたいなお客さんも、断じて、ごめんこうむりますから。それで、今日の買い物のリストは、はい、これね。魚は、ちゃんと魚辰さんに選んでもらって。あの方は、私の好みがわかっているから」
腕に抱いていた理玖の澄んだ目は、早口に話す義母の方をじっと見ていた。不意に笑いかけて、そのウエーブのついた痩せた髪に手を伸ばして触れようとしたとき、義母はその手を払いのけた。音が立つほどではなかったが、明らかにその手で理玖の手を拒絶した。
理玖はくるりと頭の向きを変えて、私の胸元に顔を埋めた。
気にするな、理玖。私は深呼吸して、理玖の背中をトントンとしながら、メモの確認をする。少しずつ、慣れていこう。
「そうですよね。初鰹の季節ですよね」
買い物メモにあった鰹について触れた。
「目に青葉、山ホトトギス、初鰹」
でしたよね。
義母は、へえ、そんなこと、知ってるんだ?という顔をして、こちらを見た。
「みんな間違っているけれど、目には青葉が正式だわ。耳にはホトトギス、口には初鰹。江戸中期の俳人山口素堂の俳句。鎌倉にてという添え書きがある」
苦情以外の義母の言葉を聞くいい機会になった。
「この時期になると、隆也さんがそう言って、鰹を食べようと誘ってくれました。お義母さんの影響だったんですね」
こちらを見て、義母は息子を思い出したようだった。
「あなたも食べたいなら、買ったらいいじゃないの」
珍しく母は、無表情のままだがそう言った。
その日は私も二階の部屋で、初鰹を厚みのある刺身で食べた。血の味がしたのを覚えている。
今日は、ついに雨が上がった。
〈雨が上がったら、会おう〉
莉子から、最後にもらったメール。
〈今日の天気は文句なしでは?〉
私は、窓から首を伸ばし、空に雲が立ち込めていないかを確認し、そうメールを送った。思わず窓を開くと、タイサンボクの花の甘い香りが、部屋まで漂ってきた。
〈たまには、海でも見に行こうか。電車に乗って。何時だったら、出られる?私は、今から病院に寄ってから行くけど、正午にはE駅に着けるよ〉
理玖はすでにブルーのTシャツとしましまのスパッツを着て、準備万端で、ベッドの上で転がっている。
〈買い物を済ませてから、私もその時間を目指すね〉
私は鏡台の前で、少しうまくなった髪の毛結びをする。
砂浜で過ごせるように、折り畳みのビニールシートや、理玖の着替えにタオルなどをショルダーバッグに詰めた。
階下に下りて、ポットに紅茶を入れる。義母に買い物リストはどこかと声をかけた。そのまま買い物に出て、一旦冷蔵庫に収めたらもうすぐにでも、青空の下に出かけたかった。理玖と一緒に。
▶次の話 実の母が、「あの子なら」と言うのだから、そこには自分の知らない夫がいるのかもしれない|うさぎの耳〈第五話〉
◀前の話 部屋の灯りを消した。束の間、眠ろう。|うさぎの耳〈第四話〉
谷村志穂●作家。北海道札幌市生まれ。北海道大学農学部卒業。出版社勤務を経て1990年に発表した『結婚しないかもしれない症候群』がベストセラーに。03年長編小説『海猫』で島清恋愛文学賞受賞。『余命』『いそぶえ』『大沼ワルツ』『半逆光』などの作品がある。映像化された作品も多い。
















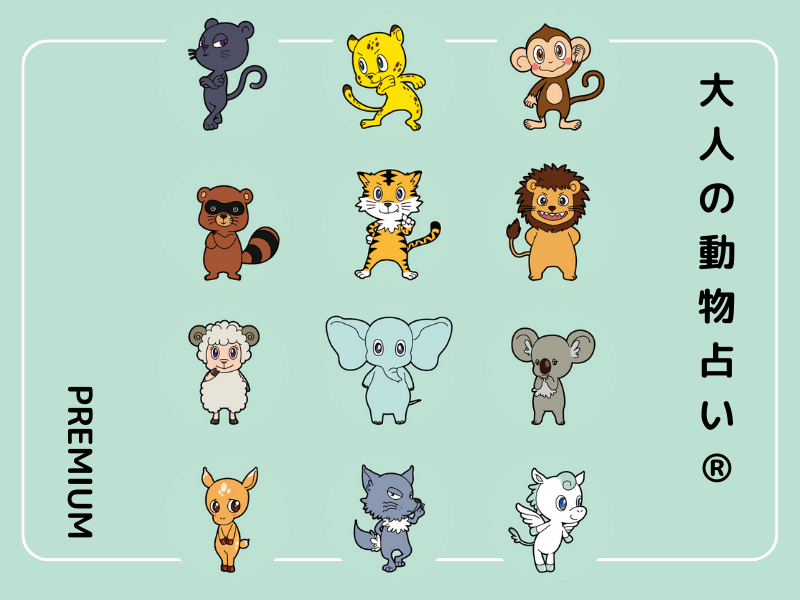




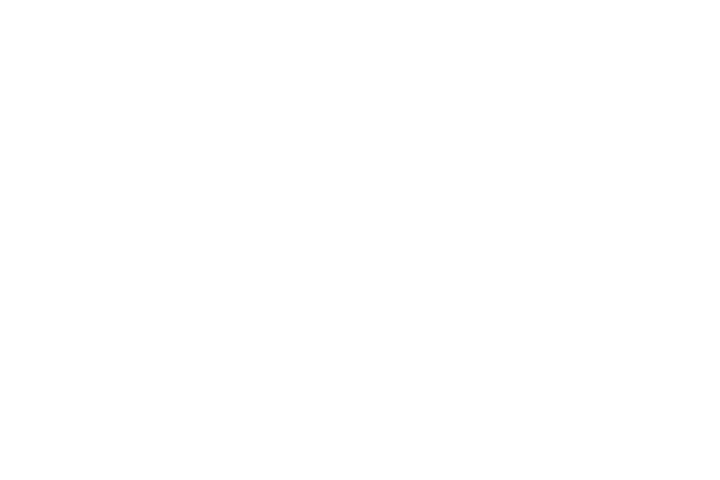
![[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひどい肌トラブルを救ってくれたのはコレでした」](http://img.kurashinista.jp/get/2025/11/26/93c18d7d3165c4c47e065f488a61a5ef.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...
[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...![[PR]体調による〈ゆらぎ肌〉に!「敏感肌フェイスケア」が頼れる理由](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/21443447263715306acb3453ec0366c1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]体調による〈ゆらぎ肌〉に!「敏感肌フェ...
[PR]体調による〈ゆらぎ肌〉に!「敏感肌フェ...![[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キッズ ベビーオリゴ®」が選ばれる理由とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2025/12/31/240a8d7521e72fb6ab5027cf72b2e102.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...
[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...![[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり・やわらか・伸び~る肌に!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/1649bec205350eddf0f29d2df2476ac8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...
[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...![[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う? 赤のジェリーでおなじみ「アスタリフト」たった7日試しただけで「わかったこと」とは!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/09/9baa7cd6aa648b5f68a397f6e1c292d8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...
[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...![[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝も、腹ペコな午後も。私たちが『超熟』を選ぶ理由って?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/26/d0a6213d838b9a06de95e683d0c14391.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...
[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...![[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家庭で効率よく向き合うケアアイテムが新登場!骨盤底筋専用EMS「SIXPAD ペリネフィット」](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/87aab1fc469c237111f888f1820fa561.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...
[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...![[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料理、ものづくり体験など魅力満載。【只見線】の旅の楽しみ方](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/6e401437f5ed3d32fe88e08a32f838e1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...
[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...







































コメント
全て既読にする
コメントがあるとここに表示されます