大人も子どもも大好きなすき焼き。記念日やお祝いの日のごちそうにも喜ばれますよね。
すき焼きは関西が発祥?
今では全国で食べられているすき焼き。そのルーツは幕末にあります。もともと、日本は仏教の影響で肉食が禁じられていましたが、神戸や横浜が開港されると、居留地にいる外国人から食肉文化が日本に伝わったといわれています。
明治になって開国すると、江戸では牛肉をネギと一緒に煮る「牛鍋」が大流行しました。
この関西の「すき焼き」でも肉が使われるようになり、やがて関東にも関西のすき焼き屋が進出したことから、関東の「牛鍋」も関西風の「すき焼き」も、合わせて「すき焼き」といわれるようになったそうです。
すき焼きの「割り下」って何で出来ているの?関東風と関西風の違いは?
関東と関西ではすき焼きの作り方が違います。
関東では汁を煮立て、そこに肉や野菜を一緒に入れて、煮込みます。一方で関西では「すき」で焼いていた時代と同じように、まずは鉄鍋で肉を焼き、しょうゆや砂糖で味付けをしていただきます。この関西風すき焼きでは、もともと野菜は、肉を食べたあとにいただいていたようです。
関東風のすき焼きを作る時に煮立てる汁を、「割り下」といいます。割り下は、だし、砂糖、酒、しょうゆ、みりん等を合わせたもの。比較的濃いめの味付けであることが多いですよね。最近では関西の家庭でも、割り下を使ったすき焼きが普及してきています。
割り下のレシピが知りたい! 家でも作れる?
割り下はいろいろなメーカーからたくさんのものが出ています。古くからのすき焼きの老舗では、秘伝の割り下などもあり、そういった名店の割り下もスーパーなどで発売されていますよね。
でも、割り下は、本来「しょうゆ」「みりん」「酒」「砂糖」などを混ぜたもののこと。一般の家庭にある調味料を使って作れるものです。もちろん、おいしくいただくには配合が大事。この機会にぜひ、おいしい割り下のレシピを研究してみましょう。
基本の割り下レシピをマスターしよう!
割り下の材料は次の通りです。
・酒…1/2カップ(100ml) ・みりん…1/2カップ(100 ml) ・しょうゆ…1/2カップ(100 ml) ・だし汁…1/2カップ(100ml) ・砂糖…大さじ3
割り下はあらかじめ作っておきましょう。作り方は、鍋に酒・みりんを入れ火にかけてアルコール分を飛ばし、火を止めて、砂糖としょうゆ、だし汁を入れ、温めます。
また、砂糖の量は好みで増減してもOK。砂糖ではなくざらめを使うとよりコクのある味わいになりますよ。
いずれにしても、酒・みりん・しょうゆ、だし汁を同量(100~120cc)にして、そこに大さじ2~3杯ほどの砂糖を加えるというのが基本。覚えておくと便利ですね。さらに好みに合わせて、しょうゆや砂糖、だし汁を加減しましょう。
すき焼きの作り方が知りたい!
ちょっとぜいたくをしたい時に食べたいすき焼き。鍋料理の中でも特別な存在ですよね。関東風、関西風、それぞれの基本の作り方をご紹介します。
関東風すき焼き(2人分)
・すき焼き用の牛肉…200〜250g
① ②
関西風すき焼き(2人分)
・すき焼き用の牛肉…200〜250g
① ② ③
※まずは鍋に焼きつけた肉そのものを味わうのが関西風です
すき焼きを作る時の注意点は?
すき焼きをおいしく食べるには、具材をちょうどよい具合に煮ることが大事。しらたきはさっとゆでて湯通しをしておく、ねぎは薄切りにする、白菜は葉と根元の部分を分けておくなど、火の通りにくい具材はきちんと下ごしらえをしておくこと。
また、関西風すき焼きは、まずは砂糖としょうゆをさっと絡めた肉を味わうのが基本。このとき、一気に焼き付ける方が、肉の風味が閉じ込められておいしくなります。
関西風のすき焼きで使う牛脂は精肉売り場などで無料で提供されていたり、すき焼き用の肉に付いてきたりしますので、ぜひ使ってみましょう。お肉に豊かな風味とコクが出ますよ。
基本の割り下を覚えておいしいすき焼きを!
割り下のレシピをマスターして、いつでもおいしく食べられるようにしたいですね。また、関東風、関西風どちらもそれぞれ魅力があっておいしそう。ぜひ食べ比べてみてください。
まとめ/吉田直子

























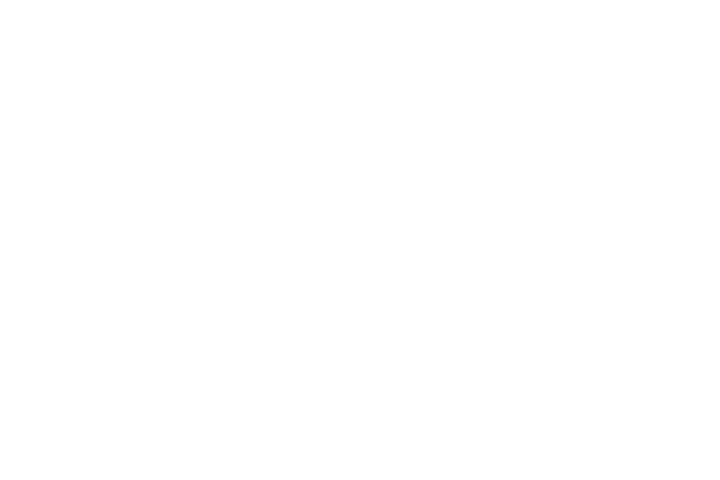
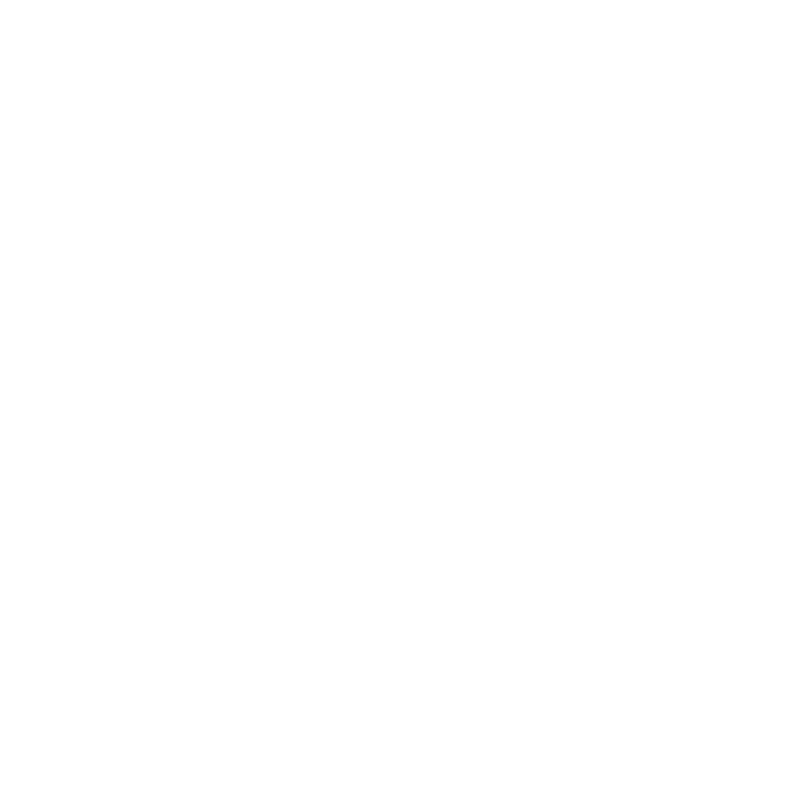
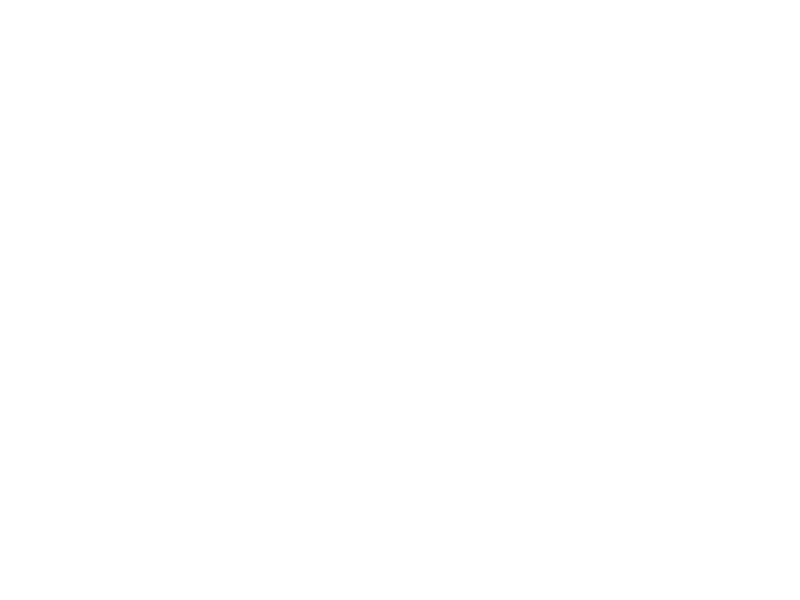
![[PR]新しい趣味友達、相談相手…既婚者でも自分に合う人を探せる!『カドル(Cuddle)』-既婚者マッチングアプリが新しい形の出会いをサポート](http://img.kurashinista.jp/get/2025/02/28/3c213006658eb4a5e136e6c65a314583.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]新しい趣味友達、相談相手…既婚者でも自...
[PR]新しい趣味友達、相談相手…既婚者でも自...![[PR]コスパ最高♪月660円の洋服預かりサービスがスゴすぎる!](http://img.kurashinista.jp/get/2025/02/27/e3cbefd1b3ab2f6fde95eb905a518b46.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]コスパ最高♪月660円の洋服預かりサー...
[PR]コスパ最高♪月660円の洋服預かりサー...![[PR]美味しさの決め手は植物油!~油の達人に聞く植物油の魅力](http://img.kurashinista.jp/get/2025/04/15/3a90c5d3cb9f44933578f0f02ea2d553.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]美味しさの決め手は植物油!~油の達人に...
[PR]美味しさの決め手は植物油!~油の達人に...![[PR]赤ちゃんへの初めてのプレゼントは名前より先に「腸内細菌」。妊娠中にゼッタイやってほしい腸活とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2025/04/15/949a2927318661cb7fb9d25c0ceb6024.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]赤ちゃんへの初めてのプレゼントは名前よ...
[PR]赤ちゃんへの初めてのプレゼントは名前よ... 「肌、いい感じ♪」が続く秘密。話題の「飲むビタ...
「肌、いい感じ♪」が続く秘密。話題の「飲むビタ... 【イベント実施報告】3月1日2日「BeMe ご...
【イベント実施報告】3月1日2日「BeMe ご... LIPSとコラボ開催!「コスメ収納」コンテスト...
LIPSとコラボ開催!「コスメ収納」コンテスト... 食品ロスならぬ「フラワーロス」を考える!楽しむ...
食品ロスならぬ「フラワーロス」を考える!楽しむ...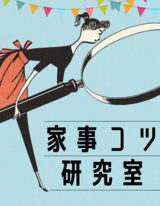






































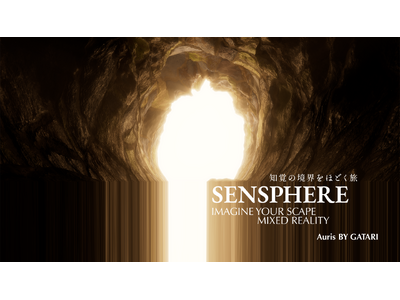

コメント
全て既読にする
コメントがあるとここに表示されます